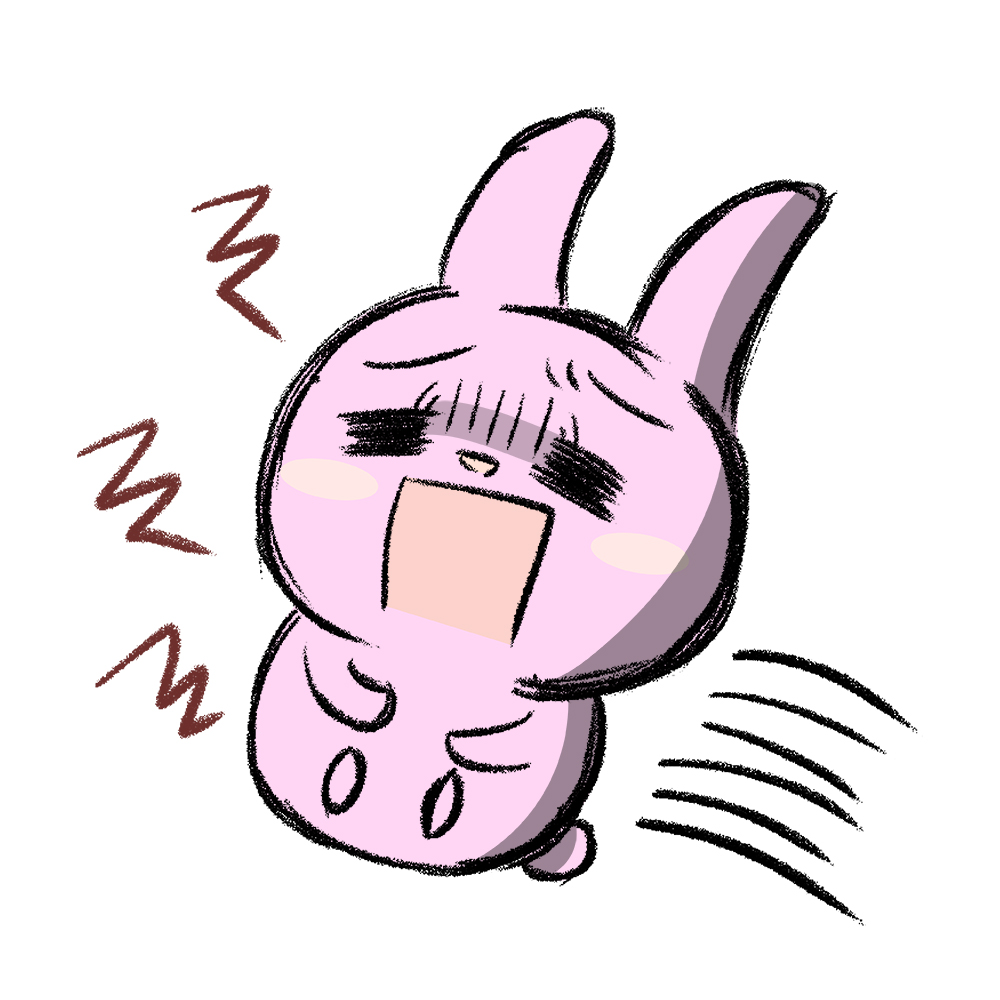浦和すずのきクリニックの鈴木です。
スマホの検索履歴が、病気の名前や症状でいっぱいになっていませんか?
「ほくろ ガン」 「頭痛 原因」
病院で検査を受けて、お医者さんから「異常はありませんよ、大丈夫です」と言われた時のことを思い出してください。
その時は「よかった」とホッとしたはずです。
でも、家に帰ってしばらくすると、またムクムクと不安が戻ってきませんか?
「もし、お医者さんが見落としていたらどうしよう」 「まだ検査で見つからないくらい、小さな異常があるのかも…」
そうしてまたスマホで調べ始め、怖い情報を見つけては、ドキドキして眠れなくなる…。 この繰り返しをしていませんか?
「病気なのか、そうじゃないのか、ハッキリさせて安心したい」
しかし、どれだけ検査をしても、どれだけネットで調べても、「100%絶対に大丈夫」という証拠は見つかりません。
「もしかしたら…」という「あいまいさ」をゼロにすることはできないのです。
実は、今あなたが苦しいのは、体の不調そのものよりも、この「答えの出ない『あいまいさ』を、なんとかして解決しようとしていること」にあるのかもしれません。
白黒つけられないことを、無理に白黒つけようとすると不安を強めてしまう「悪循環」に入り込んでしまいます。
そこでこの記事では、まず「不安が強い時によくある3つのパターン」についてお話しします。
その上で、多くの方が抱く「なぜ検査で異常がないのに、痛みや違和感が消えないのか?」という疑問についても、その仕組みを分かりやすく解説します。
「症状」ではなく「パターン」と「仕組み」を知ることで、今の苦しみを和らげるヒントが見つかるかもしれません。 ぜひ、最後まで読んでみてください。
「白黒はっきりさせたい」という気持ちから、私たちは無意識にいろいろな行動をとります。 しかし、その行動こそが、逆に不安を長持ちさせる燃料になっていることがあります。
以下の3つのパターンに心当たりはありませんか?
① 体の「確認」がやめられない
「しこりがないか、何度も触って確かめる」 「鏡で喉の奥をずっと観察する」 「排泄物の色や形を毎回チェックする」
気になるところをチェックしたくなることはよくありますが、 1日に何度も、あるいは何十分もチェックし続けていないでしょうか?
実は、人間の感覚は「意識を向ければ向けるほど鋭くなる」という性質があります。
「異常があるかもしれない」と思って触り続ければ、普段なら気にならない程度の筋や骨の出っ張りさえも、「おかしなしこり」に感じられてしまうことがあります。
安心したくて触っているのに、触ることで余計に不安な感覚を作り出してしまう。これが一つ目のパターンです。
② ネット検索で「安心」を探そうとする
「症状 病気」 「この年齢でガンになる確率」
スマホで検索をして、「怖い病気ではない」という情報を探そうとしていませんか? しかし、医学書やネットの情報には、あらゆる可能性(たとえ0.01%でも)が書かれています。
不安になっている時は、99個の「大丈夫」という情報よりも、たった1個の「怖い情報」をキャッチしてしまうクセがあります。
「安心」を探して検索を始めたはずが、結果として「新しい恐怖」を拾ってきてしまう。これが二つ目のパターンです。
③ 「大丈夫」と言われても、すぐに疑ってしまう
病院で「異常なし」と言われた直後は安心するのに、数日、あるいは数時間でまた不安になっていませんか?
「本当に大丈夫かな? 見落としがあるんじゃないか?」と同じ場所を疑い続けたり、 「胃は大丈夫だったけど、今度は頭が痛くなってきた」と別の場所が気になり始めたり。
場所が変わることもあれば、同じ場所のこともありますが、共通しているのは「検査結果による安心感が、すぐに消えてしまう」ということです。
ここまで読んで、「私が気にしすぎなのは分かった。でも、実際に痛みがあるんです! 気のせいなんかじゃありません」と思われたかもしれません。
確かに人によっては、そこに「不快な感覚」があるのは紛れもない事実です。
では、検査で異常がないのに、なぜこんなに辛い感覚があるのでしょうか?
その理由は、不安のせいで「感覚の感度が上がりすぎている」からかもしれません。
実際に「痛い」のですが、それは病気があるからではなく、心配しすぎるあまり、体からの信号を何倍にも強く受け取ってしまっている状態です。
本来、私たちの体は、胃腸が動く時や、心臓が動く時に、常に小さな音や揺れを発しています。
元気な時は気になりませんが「どこか悪いのではないか?」と不安になると、体はこの小さな感覚をすべて拾い上げてしまいます。
夜、寝ようとしている時に、時計の秒針の音が急に大きく聞こえるのと同じです。
時計の音が大きくなったのではなく、あなたの「聞こうとする耳」が鋭くなっただけですよね。
つまり、今の体はどこかが壊れているのではなく、「体を守ろうとして、センサーが敏感になりすぎている」だけなのかもしれません。
ここまでのお話で、今の苦しみの正体が「体の病気」ではなく、「敏感になりすぎたセンサー(不安)」にあることが分かってきたかと思います。
では、どうすればこのセンサーの感度を元に戻せるのでしょうか?
それには、不安にエサを与えるのをやめて、「不安への反応を止める練習」をしていく必要があります。
具体的には、以下の3つを意識してみてください。
①「検索」という反応を止める
不安になった瞬間、反射的にスマホで検索していませんか?
検索すれば安心できる気がしますが、実は逆です。
検索することは、脳に「これは緊急事態だ!」と教え込むことになり、余計にセンサーを敏感にさせてしまいます。
不安になっても、「検索したい」という衝動をグッとこらえて、スマホを置いてください。 最初は怖いかもしれませんが、検索せずに時間が経てば、ピークだった不安は必ず波のように下がっていきます。
「検索しなくても大丈夫だった」という経験を積み重ねることが、一番の薬になります。
②「確認」をやめて、放っておく
気になるところを指で押したり、鏡で見たりするのは、傷口をいじって広げているのと同じです。
触れば触るほど、そこが刺激されて余計に気になります。
どんなに気になっても、「あえて触らず、そのままにしておく」と決めてください。
「確認しないと手遅れになるかも」という不安が襲ってくるかもしれませんが、そこを乗り越えて「確認しない」という行動を選び続けることで、脳は少しずつ「あ、警戒しなくても平気なんだ」と学習し始めます。
③ 「体の外」のことに集中する
痛みや違和感がある時、意識は自分の「体の内側」に釘付けになっています。
これを意識的に「目の前のこと(外側)」に向ける練習です。
無理に痛みを忘れようとする必要はありません。痛みがあってもいいので、
・今やっている仕事に集中する
・家事を淡々とこなす
・目の前の人と会話をする
このように「痛みがあるままで、普段通りの生活を送る」ようにしてみてください。
「体の内側」ではなく「目の前の現実」にエネルギーを使う時間を増やすことで、過敏になっていたセンサーのバランスが整っていきます。
不安を感じたら「検索」や「確認」を繰り返すことはやめましょう。
なぜなら、あなたが求めている安心は、ネットの中にも、検査室の中にもないからです。
今の状況から抜け出すために必要なこと。
それは、病気を見つけることではなく、「不安になった時の行動」を変えることです。
今まで通りの行動を続ければ、不安もそのまま続きます。
しかし、行動を変えれば、必ず結果は変わります。
もし、一人で今の習慣を変えるのが難しいと感じたらカウンリングを受けにきてください。
一緒に解決策を考えていきましょう。