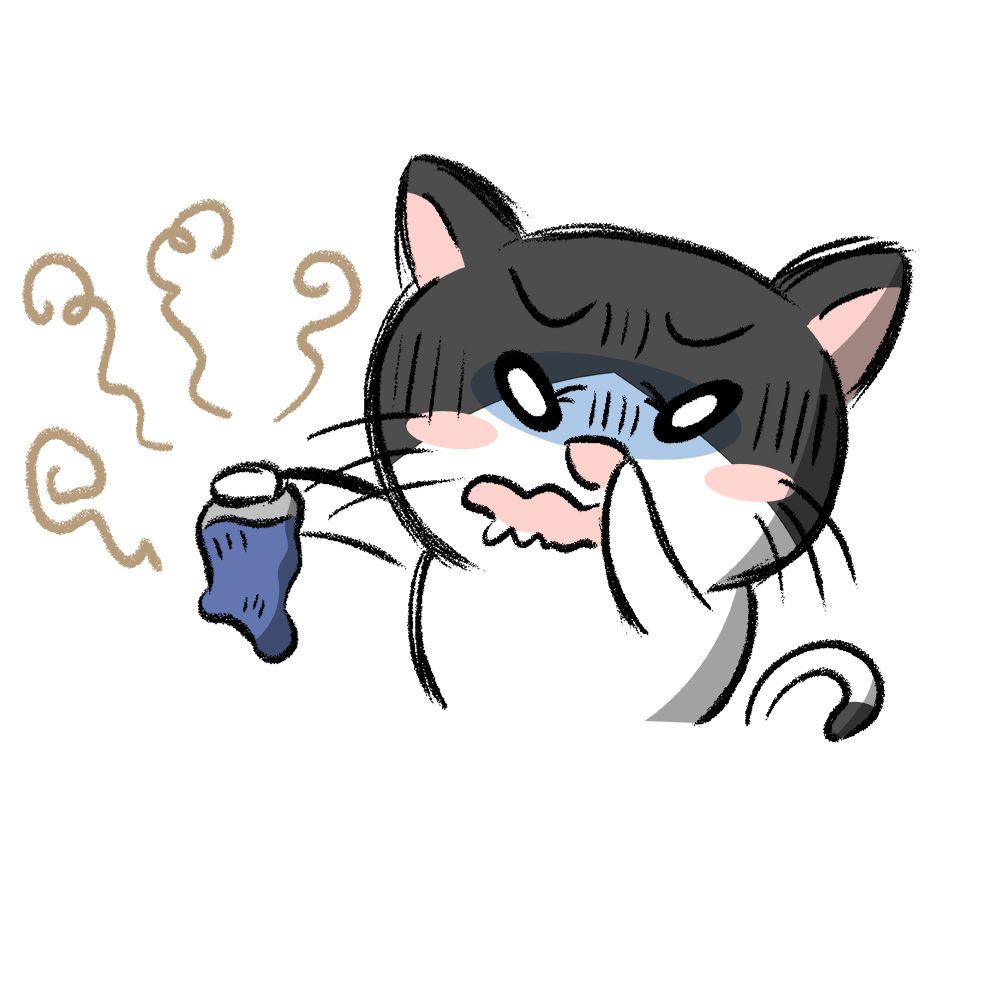
浦和すずのきクリニックの鈴木です。
友人と話していると「相手がふと顔をしかめたように見えたのは自分の口臭がくさいからでは?」
電車で隣に座った人が、少しして別の車両に移っていった。
会議中、向かいの席の同僚が、しきりに鼻をすすっている。
これも全部自分の臭いが原因だと考えて不安になっていませんか?
もしかしたら「自己臭恐怖症」かもしれません。
これは正式な診断名ではなく「自臭症」「嗅覚関連付け症候群」などと呼ばれており強迫症や社交不安症と関連が深いと言われています。
この記事では知ることができることは以下のことです。
・不安が強くなる仕組み
・自分のにおいに振り回されなくなるための具体的に対処法「3つのステップ」
不安を改善して臭いから自由になるためのきっかけにしてください。
なぜ、その尽きることのない不安から、抜け出すことができないのでしょうか。
実は、あなたの心は巧妙な「悪循環」に陥っています。
その悪循環は、主に2つの『クセ』によって強力に維持されているのです。
【ワナ1】すべてを「くさい証拠」に変えてしまう考え方のクセ
不安になった時に「自分はくさい」ということを大前提として、世界を見るようになります。
これが一つ目の「考え方のクセ」です。
例えば、誰かが鼻をすすったり、咳をしたりすると、瞬時にこう考えます。
「私の臭いが原因だ」と。
- 電車で隣の人が席を立った → 「くさくて避けられた」
- 職場で窓が開けられた → 「くさいから換気されている」
- 友人が顔をしかめた → 「くさいと思われた」
実際には、全く別の理由があったとしても、心は「自分が臭いことの証拠」として、あらゆる出来事を自動的に変換してしまいます。
こうした思考のクセは、過去に臭いを指摘された経験や、誰かの些細な言動といった、ふとした「きっかけ」によって形作られることがありますが、今やこの「考え方」そのものが、あなたの不安を支える強力な柱になってしまっているのです。
【ワナ2】安心するための行動が確信を強める行動のクセ
「自分は臭い」という確信があれば、当然、その臭いを何とかしようと対策をします。
しかし皮肉なことに、この行動こそが、あなたの確信を岩のように固めてしまう二つ目の「行動のクセ」なのです。
- 一日に何度も体を洗い、肌が痛くなるまでこする。
- 消臭スプレーやミントタブレットが手放せない。
- そもそも、人と会うのを避けるようになる。
こうした対策行動は「安全行動」「回避行動」と呼ばれます。
安心のためにやっているこれらの行動が実際は不安を強め、さらに「自分はくさいに違いない」という確信度を高める可能性があるのです。
なぜなら、その行動を取るたびにあなたは無意識に「この対策がなければ、私は臭いんだ」と、自分の脳に言い聞かせているのと同じことだからです。
行動すればするほど「対策なしの自分は危険だ」という学習が強化され、「自分は臭い」という”確信”から、ますます抜け出せなくなります。
「考え方のクセ」が「臭いの確信」を強め、「行動のクセ」がそれを強固なものにする。
この2つが互いを強化し合うことで、決して抜け出せない強力な「悪循環」が生まれるのです。
しかし、この2つのワナの仕組みがわかれば、対策も明確です。
次の章では、この「考え方」と「行動」に直接アプローチして不安を改善する「3つのステップ」をご紹介します。
※対処法については人それぞれなので、一例として参考にしてください。
ステップ1:自分の”不安パターン”を書き出す
最初のステップは、あなたの不安がどのようなパターンで起きるのかを、客観的に分析します。
以下の4つの項目を書き出してみましょう。
①状況: どんな時に不安になりますか?
例:休憩室で、同僚のと二人きりになる
②自動的に浮かぶ考え: その時、頭に浮かぶことは何ですか?
例:「私の口臭がキツイと思われているに違いない」
⓷最悪の予想: その結果、相手がとるであろう「行動」を具体的に予想します。
例:「同僚はハンカチで鼻を覆う」「同僚が3回以上、鼻をすする」「5分以内に席を立つ」
④いつもしている対策(安全行動): その最悪の事態を避けるために、いつも何を行っていますか? 例:「会話中は常にマスクをつける」「ミントタブレットが手放せない」「相手と2m以上の距離を保つ」
ステップ2:「対策」なしで行動してみる
次のステップは、その不安な状況に、あえて「いつもしている対策(安全行動)」を一つだけやめて、飛び込んでみることです。
「この対策のおかげで助かっている」という考えを実験を通して検証します。
ステップ1で書いた不安のパターンを使ってみましょう
まず①の「不安になる状況」をあえて作り出し、④の「いつもの対策(安全行動)」をあえて使わずに挑戦してみます。
すると、②で浮かんできた不安な考えが実際に頭に浮かぶかもしれません。
そのときに、「③で予想した最悪のことが、本当に起こるのか?」を冷静に確かめてみるのです。
例
・会社の同僚とマスクなしで話をする。
・食事後、ミントタブレットを使用せずに同僚と話をする
・同僚の席の目の前に座り会話をする
<実行中のコツ:注意を「外側」に向ける>
実行中に不安になったら、心の中で「実況中継」を試してみてください。
例:「今、同僚はコーヒーを飲んでいるな」「窓の外の雲が動いているな」「あ、仕事の話で笑った」
これをやる理由は私たちの注意は不安になると自分の「臭いのでは」という考えや動悸など「内側」に向きがちです。
そうすると不安にのまれ、現実をきちんとみることが難しくなります。
注意を「外側」の現実に向けることでより客観的に状況を評価できるようになります。
ステップ3:「予想」と「現実」を比べる
ステップ2で行動した結果、何が違ったか、どんな発見があったかを書き出しましょう。
例
| 最悪の予想(やる前) | 実際に起きたこと(やった後) |
| 鼻をハンカチで覆う | 何をせず話していた |
| 3回以上鼻をすする | そんなことは一度もなかった |
| 5分以内に席を立つ | 休憩時間中話していた |
この答え合わせの作業をすることで「思ったより何も起きなかった」という経験が多く得られ、少しずつ「自分がくさいのではないか?」という不安が少なくなってきます。
【予想に近いことが起きた場合】
それは「解釈」ではないかを検討してください。
「鼻を一回はすすった」のは事実でも、「私の“せい”で」というのは、あなたの「解釈」かもしれません。
まずは起きた「事実」と、自分の「解釈」を冷静に分けてみましょう。
再度同じ実験をしてみて確かめるの一つの手です。
この3つのステップを、少しずつレベルを上げながら繰り返していくことで、あなたの思考のパターンは、少しずつ現実に基づいた新しいものに変わっていくでしょう。
もし、一人でこのステップに踏み出すのが怖い、振り返りがうまくできないと感じたら、認知行動療法の専門家を頼ってください。
カウンセリングでは、あなたに合った最適な計画を一緒に立て、悪循環から抜け出すためのお手伝いをします。

